JSBi名誉会員就任記念講演
| 日時・会場 | 9月3日(水)15時20分〜16時50分 第1会場 |
| 座長 | 浜田 道昭(早稲田大学, 産業技術総合研究所, 日本医科大学) |
AL-1
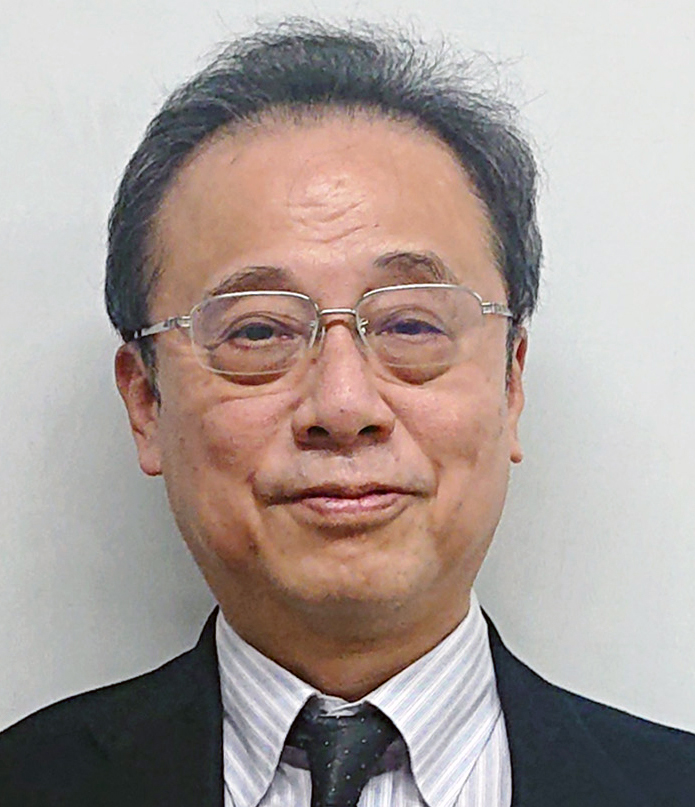
清水 謙多郎 先生
(東京大学 名誉教授・大学院農学生命科学研究科 特任教授、日本女子大学 理学部 数物情報科学科 特任教授)
演題題目:バイオインフォマティクスの人材養成の一つの実践例について
講演要旨:東京大学のアグリバイオインフォマティクス教育研究ユニットは、2004年に発足し、20年以上にわたりバイオインフォマティクスの人材養成に取り組んでいる。農学生命科学(アグリバイオ)の分野を主な対象として設立されたが、基礎や方法論の講義は、バイオインフォマティクス全体を広くカバーするもので、各領域の専門家による実習形式の授業が行われている。受講者数は、本年度中に9000人を越える見込みである。カリキュラムは、当初、本学会のバイオインフォマティクス教育カリキュラム(第2版)と連携していたが、分野の発展に応じて内容の更新を続けている。本ユニットは、大学院生や社会人を対象とし、実践的なスキルの習得を重視するだけでなく、受講者の研究支援も受け付けてきた。そうした活動を通して多数の実験研究者と共同研究が生まれた。本学会でも、アグリバイオインフォマティクス研究会の発足につながった。現在、バイオインフォマティクスの人材養成は多くの機関で展開されており、応用分野、対象者、求められるスキル水準も多様化している。こうした多様性や分野のもつダイナミックな特性を踏まえつつ、より効果的な人材養成を実現していく上で、学会の役割は今後ますます重要になると考える。
AL-2

冨田 勝 先生
(慶應義塾大学 名誉教授、一般社団法人 鶴岡サイエンスパーク 代表理事)
演題題目:AI時代における人間研究者の役割 ~脱優等生のススメ~
講演要旨:「バイオインフォマティクス」は「システムバイオロジー」「オミクスバイオロジー」「データドリブンバイオロジー」など、さまざまな名前で発展してきたが、いずれにしても生命科学の本質は結局「データサイエンス」である。そして今後は、「AIドリブンバイオロジー」が主流となっていくに違いない。
生成AIは、実験計画の立案やデータ分析、考察、先行研究との比較、論文執筆など、優等生的な作業を高い精度でこなすようになり、人間はそれを最終チェックする程度になるであろう。その一方で、「誰も考えたことがない」とびっくりするようなアイデアや、時に周囲から批判されるような「やんちゃ」なことは決して提案しない。つまり生成AIは、非常に優秀な「優等生」であるが、ブレークスルーをもたらす「イノベーター」ではないのである。
では、人間に求められるものは何か?
私は1980年代、第二次AIブームの最中にアメリカでAIを研究し、その後33歳で生命科学に転身した経歴がある。思いがけず訪れた第三次AIブームの今こそ、改めて「AIと人間の違い」を真剣に考えるようになった。
本講演では、そんな経験をふまえて、AIと共存するこれからの研究スタイルと、人間の役割とは何か、についての私の考えを述べる。